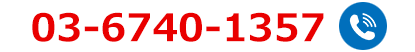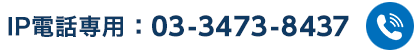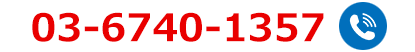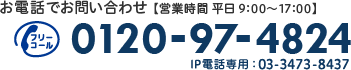計測器・測定器玉手箱
サンプリングと立ち上がり時間
サンプリングと立ち上がり時間
アナログ信号をデジタル化して解析する場合には、デジタル化の際に入り込む誤差を吟味しておく必要があります。
測定器でも、デジタル化に至る設定が適切でなければ能力を活かせません。
どんなに優れた解析を行っても、不適切なデータからは精度の高い結果は得られないからです。
アナログ信号のデジタル変換は、滑らかなアナログ波形( 信号) を階段状の波形に近似することに他ならず、誤差の少ない正確な解析のためには、縦・横共に階段をできるだけ細かく刻むべきであることは疑う余地はありません。
まず初めに押さえておきたいのは、信号レベルとAD 変換器のレンジとの関係です。
例えば、図1で黄色で示した信号を変換する場合、同図の(A)のように信号のフルスケール値とAD 変換器のフルスケール値(レンジ)が近ければ良いのですが、(C)の様に変換器のレンジが過大で感度が不足すると、分解能を十分に活かすことができません。
例えば、16ビットのAD 変換器を使ったとしても、8ビットかそれ以下で変換したのと同じになってしまい、16ビット分のダイナミックレンジを有する結果は得られないことになります。
反対に、信号レベルに対してAD の感度が高すぎたりオフセットがずれていたりすると、回路が飽和して正しいデータに変換されませんし、回路が飽和から回復するまでに思わぬ時間がかかることもあります。
次に、時間軸方向を考えます。
アナログ信号の持つ周波数スペクトルとサンプリング速度の関係は、「サンプリングには、アナログ信号の持つ最高周波数成分の2 倍以上のスピードが必要」という「ナイキストのサンプリング定理」が出発点です。
図2は、実際にどうなるのかを示したものです。
サンプリング周波数を8kHzとした場合、2kHzの信号はサンプリング定理の条件内(8kHz>2×2kHz)なので、波形を正しく再現できます。
他方、条件を超えた6kHzの信号(8kHz<2×6kHz)を入力すると、サンプリングの結果は6kHzではなく2kHzを入力したときと同じになって、6kHzの信号があたかも2kHzの信号であるかのように見えてしまいます。
このように、サンプリング定理の限界周波数を超えた信号が、本来とは異なる周波数に変換されて本来の信号内に侵入する現象をエリアジング(aliasing)と言います。
データにエリアジングが入り込まないようにするには、一般にはA/D 変換器の前段にローパスフィルタを入れて最高周波数を制限します。
このためのフィルタが、アンチエリアジングフィルタ(anti-aliasing filter)です。
波形を乱したくない等の理由でフィルタを入れないこともありますが、この場合は、速度的に十分な余裕を持ってサンプリングしなければならないのは言うまでもありません。
また、解析の際に、ADした全てのデータを使わずに間引いて使うことがありますが、データを単純に間引くことは、サンプリングを遅くするのと同じですので、エリアジングが発生します。
このため、オシロスコープなどでは間引き表示に際して間引きの間にあるデータ中の最大値を表示する等の処理が施されます。
ここからは、パルスの立ち上がりなど信号が急激に変化する部分とサンプリングとの関係を取り上げます。
第一に考えなければならないのは、アンチエリアジングフィルタの影響です。
最終的に観測される立ち上がり時間は、AD の前段が持つ立ち上がり時間(アナログ周波数特性)の影響を受けます。
一方、アンチエリアジングに必要なフィルタは急峻な減衰特性を持ち、フィルタの時間応答も複雑です。
従って、フィルタの挿入に当たっては、少なくとも、ステップレスポンスがどのようになっているかを予め確認しておくことが望まれます。
立ち上がり時間を求めるために必要なサンプル点数はどうでしょうか。
信号の立ち上がり区間において十分なサンプルが得られれば再生波形から立ち上がり時間を求めることができますが、高速な信号に対してはサンプルスピードが足りず、わずかなサンプルから立ち上がりを推定しなければならないことも多いものです。
図4は、こうした限界付近におけるサンプル点の位置と、その結果から推定される立ち上がり時間の関係を示したものです。
同図で、赤い点と緑の点は、同じサンプリング周期ですが、点を直線で結んだ傾斜から計算される立ち上がり時間は1.6倍もの開きが生じています。
このことからも、立ち上がりの間に十分な数のサンプルが得られなければ立ち上がりを正しく再現できないことがわかります。
立ち上がり部分の持つスペクトラム(高調波成分)とナイキストの定理から考えても明らかな結論とも言えますが、実際にはよく遭遇するシーンでもあります。
ちなみに、立ち上がりの再生はサンプル点間の補間方法などにより誤差が異なり、直線補完は立ち上がりのような急峻に変化する信号評価には適した補間法とされています。
しかしながら、いずれにしても高速な立ち上がりを有する信号のサンプリングデータから立ち上がりを評価する場合は、アナログ帯域を満足した上で、点数を十分に確保できるサンプルスピードを選ぶ必要があります。
信号の速い変化をデジタイズする場合には、サンプルスピードに加えて、サンプリングクロックのジッタについても確認しておきたいところです。
サンプリングのクロックにジッタが含まれると、波形が歪んで取り込まれてしまうからです。
このため、オシロスコープなどの測定器では、十分に低ジッタのクロックが供給されるよう配慮されていますが、速度の限界付近ではジッタの影響が現れないわけではありません。
例えば、高速ADを実現するためにクロックのタイミング(位相)が異なる複数のAD変換器を並列にして、それぞれの出力を再合成するインタリーブ方式が採られているものがありますが、クロックの位相差に誤差があると結果としてジッタを生じ、波形の細部が歪んで見えることになります。