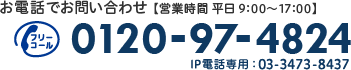計測器・測定器玉手箱
方形波の性質と計測上の扱い
方形波の性質と計測上の扱い
電子回路の多くがデジタル化されたのに伴い、計測の対象となる信号も、方形波やパルス状の波形である場合が多くなりました。
ベテランの技術者は、方形波のことを「矩形波(くけいは)」と呼んだりもします。
デジタル信号処理の世界では信号を1と0の符号列として扱われます。
ところが、実際のシステムや回路中ではデジタル信号をアナログの方形波信号として評価しなければならないことが多くあります。
また、最近ではスイッチング電源やデジタル・オーディオアンプのように、回路そのものがオンオフのスイッチで構成され、動作波形が方形波となるものも多くなりました。
方形波の性質と扱いはエレクトロニクスの基本でもあり、多くの方が過去に教科書などで学ばれていると思いますが、ここでは、電子計測を意識しながら、それらを復習することにします。
一般に「方形波 (square wave)」と言った場合は、図1の上段に示したようなハイとローに留まる時間が等しい信号を意味します。
しかしながら、実際の回路中などではハイレベルの時間とローレベルの時間は必ずしも同じとは限りません。
その場合、ハイとローの時間比率あるいは繰り返しの周期に対するハイレベル(もしくはローレベル、論理が1となる期間)の比率をデューティ比(duty factor / duty ratio)と呼びます。(図2)
従って、通常の方形波のデューティ比は1:1、あるいはデューティ50%です。
さて、最も基本的な信号とされる正弦波と今回採りあげる方形波との大きな違いはそのスペクトラム(spectrum:周波数成分の分布)にあります。
従って方形波を扱う場合は、そのスペクトラムを頭に描けるようになることが第一歩だと言えます。
ひずみの無い正弦波のスペクトラムは、繰り返し周波数成分だけです。
これに対して方形波は多くの高調波成分を伴います。
その様子はFFアナライザやスペクトラムアナライザを使って見ることができますが、理論的には方形波の波形をフーリエ級数展開することで求まります。
計算の過程はほかに譲るとして、ここではその結果をおさらいします。
やや教科書的な内容になりますが、しっかり抑えておきたいポイントだからです。
まずはデューティ比1:1の方形波です。
この場合、繰り返し周波数(基本波)のほかに3次、5次、7次、・・・という具合に奇数次の高調波成分(基本波の奇数倍の成分)を含みます。
反対に、2次、4次というような偶数次(基本波の偶数倍の)成分は含まれません。
偶数次成分を持たないのは、繰り返しの中心で点対称となる信号に共通した性質ですので憶えておくと良いでしょう。
各成分の大きさは、基本は成分の大きさを1とすると、3次成分は1/3で、5次成分は1/5、・・・と続き、N次の高調波成分の量は1/Nになります。(図3)
これも憶えやすい関係です。
留意したいのは、「N次になっても1/nにしかならない」という事実です。
デシベルで表現すると6db/octという穏やかな減衰です。
例えば、高調波成分が-20dB (1/10)を下回るのは第11次高調波以降であり、周波数が1000倍に達してやっと-60db (1/1000)になる、というわけです。
実際の方形波は波形の角が鈍っていることがほとんどなので、高次の高調波成分はこれより少ないのですが、N次になっても1/nにしかならないという事実からは以下の二つの問題が見えてきます。
ひとつは、方形波を扱うには周波数帯域の広い回路や伝送路が必要になると言うことです。
このことは、計測器で方形波を扱う場合も同じです。
計測器は繰り返し周波数やクロック周波数よりも十分に広い周波数帯域を持ったものでなければなりません。
大まかな目安として方形波として誤差無く扱うには、繰り返しの10~20倍は必要とされています。
ただし、最近の高速デジタル信号では回路の周波数帯域が追いつかず、繰り返し周波数の3~5倍程度と方形波として扱える限界付近で動作しているものもあります。
図4に3次高調波および5次高調波までで打ち切った場合の合成波形を示します
方形波が高次の高調波を含む事実から導かれるもう一つの問題は、方形波つまりデジタル信号がノイズとしてほかの回路などに与える影響です。
前述のように方形波は高次の高調波を含み、その減衰はなだらかです。
別な言い方をすれば、方形波は思いもよらぬ高い周波数までノイズをまき散らす可能性があります。
例えば、クロック周波数が10MHzのデジタル信号から発生したノイズがGHz帯の回路に影響を与えるといったことも珍しくありません。
従って、方形波を扱う際には、併行して十分なノイズ対策を施すよう心がけてください。
方形波のスペクトラムでもう一つ留意しておきたいのが、各高調波の位相です。
方形波は基本波と各高調波が合成された波形だと考えることができますが、その場合の各高調波の位相が揃っていなければ、たとえ各好調波成分の値が正しくとも方形波にはなりません。
図5は各高調波のレベルは変えずに位相だけを回転させた場合の波形を示したものです。
方形波とは全く異なる波形になっています。
従って、方形波をフィルタなど高調波の位相が回転する回路に通す場合は細かな注意が必要になります。
余談になりますが、人間の耳は各調波間の位相関係には比較的鈍感なため、図5のような波形と方形波の音を聞き分けることができず、多くの人は方形波と同じ音に聞こえるといいます。
さてここまでは、方形波のデューティ比が1:1のスペクトルを元にしてきました。
しかしながら、実際のデジタル回路などではデューティ比1:1というのはクロック信号などに限られ、むしろ希です。
ほかの多くのデジタル信号はデューティが1:1以外または刻々と変化しています。
そうした場合のスペクトルについても基本的な性質は心得ておかなければなりません。
デューティ比1:1の方形波では奇数次高調波だけが存在し、その大きさはN次で1/Nであると述べました。
実は、この関係は図6に示した用にSin(x)/xのカーブが深く関係しています。(図に黄色で示したのがスペクトル)
そして、高調波のスペクトルがSin(x)/xのカーブ上にプロットできるという関係はデューティを変化させても変わりません。
もう少し詳しく見ていきましょう。
まず、図6で繰り返し周波数を変えると、Sin(x)/xのカーブが周波数方向に伸び縮みします。
例えば、周波数を下げるとSin(x)/xのカーブも左(周波数の低い側)に圧縮された形になり、スペクトルの間隔が狭くなります。
反対に周波数を上げればSin(x)/xのカーブは周波数の高い方向へ全体が引き延ばされた形になります。
次に、デューティ比を変化させると、周波数を上げた時と同じようにSin(x)/xのカーブは高い方向へ全体が引き延ばされた形になります。
ところが、スペクトルが立つのは繰り返し周波数の整数倍の位置のままです。(図7)
従って、デューティ比1:1では存在しなかった偶数次の高調波も発生します。
ちなみに、Sin(x)/xが最初にゼロになる周波数は方形波がハイになる時間(図7下のτ)分の1に相当する周波数です。
なお、デジタル信号では、1と0即ちハイとローがさまざまに組み合わされます。
例えば10101010101010の場合の繰り返し周波数はクロック信号周波数の1/2になります。
また、100010001のような場合はクロック信号の1/4でデューティ比が1:3である場合と同じです。
従って、符号が連続するデジタル信号では、スペクトラムも時々刻々と変化することになります。
ところで、繰り返し周波数を限りなく下げると同時に、デューティも限りなく小さくするとスペクトラムはどうなるでしょう。
周波数を下げるに従ってスペクトラムは密集していきます。
同時にデューティを小さくしていくとSin(x)/xが右方向へ延び、Sin(x)/xがゼロになる1/τの周波数は高い側へとシフトしていきます。
両者が極限に達した状態を考えると、スペクトラムは周波数上で連続し、かつ無限の周波数まで一定で減衰しないことになります。
つまり、極限では、あらゆる周波数成分を等しく持つことになります。
これを時間軸で考えると、周波数を下げることは信号が孤立する方向、つまり単発現象に近くなることに相当し、デューティを小さくしていくことは方形波が細いパルスになることに相当します。
それらの極限は、孤立した幅のないパルスです。
こうしたパルスはインパルス(impulse)と呼ばれます。
つまり、「インパルスは、あらゆる周波数成分を含有している信号である」という結論が導かれます。
この性質を利用してインパルスを計測用の信号源として利用する場合もあります。
例えば、比較的大型の構造物の振動特性(伝達関数)を計測する場合などには、計測対象をハンマー(インパルスハンマー)で叩いて発生する衝撃波(インパルス)を信号源として解析します。
なお、全周波数にスペクトラムが分布しているとすると、パルスのパワーを論議する際に矛盾を生じるので、単位インパルスという別の定義が必要になります。
ですが、方形波が孤立し、短い単発パルスとして存在するとスペクトラムが高い周波数まで一様に分布するする方向へ向かうという性質に変わりはありません。
具体的な問題例を挙げれば、スイッチの切り換えなどで生じる鋭いパルス状の信号は、広い周波数に亘って一様にノイズを放射する危険性を持っています。
以下は、計測器で方形波を扱う際の実戦的な話題です。
デジタル信号をアナログの方形波として評価する場合の主要なパラメータとしては、信号のレベル、繰り返し周期(周波数)、デューティ比、ジッタなどのほかに、立ち上がり時間やオーバシュートやリンギングなど波形の品位に関する項目があります。
オーバシュートやリンギングは、波形の過渡的な変動量を表します。
また、波形の立ち上がり部分の変動をプリシュートと呼んで区別することもあります。
多くの場合、立ち上がりと立ち下がりでは上下対称の波形となりますが、立ち下がり部分の行き過ぎ量をアンダーシュートとして区別して扱うこともあります。
例えば、映像信号などではローレベルに落ちる部分の暴れが画質に大きな影響を与えるため、アンダーシュートの量が問題になります。
なお、信号が立ち上がってから許容される範囲内に落ち着くまでの時間を、セトリングタイム(settling time)として定義することもあります。
また、デジタル信号をアナログ波形として評価する場合の波形品位を総称して、シグナルインテグリティ(signal integrity)などと呼ぶことがあります。
ちなみに、「立ち下がり」という語は日本語として違和感を憶えるかもしれません。
しかしながら、電気用語としては普通に用いられています。
図9は方形波の立ち上がり時間をオシロスコープで計測する様子を示したものです。
一般的に方形波の立ち上がり時間は全体の10%から90%に至る時間をもって定義されます。
ただし、最近の高速デジタル信号などでは20%から80%までの時間と定義している例もあります。
次は方形波の大きさを計測する場合の注意です。
オシロスコープなどで波形を観測する場合は、ハイレベルとローレベルの差即ちpeak to peak voltage [VP-P]で表記するのが一般的です。
この場合、ハイとローの絶対値の情報は含まれないので、0Vと3Vでも±1.5Vでも同じVp-p値になってしまうことに注意してください。
必要があれば、0V-3Vや±1.5Vのように表記するのが適当でしょう。
方形波をAC結合(コンデンサを介した信号接続)で観測する場合はさらに注意が必要です。
まず繰り返しの比較的遅い信号の場合は波形の水平部分が斜めに見える「サグ」に注意します。
高速の信号の場合は、計測器の周波数特性(前述)のほかに、波形の持つ直流分に対する注意も必要です。
方形波はハイとローのレベルが正負同じであっても、デューティ比が50%の時を除いて波形は直流分を持ちます。
直流分を含む方形波をAC結合で観測すると、波形は直流分を打ち消すように上または下にシフトします。(図11)
図11でハッチングを入れた面積が等しくなるように移動するわけです。
従って、もしデューティ比が時間と共に変化する信号があったとすると、波形全体があたかもフラフラと上下に変動する信号のように見えます。
次は、方形波を電圧計で測る場合の指示についてです。
特に断りのない場合、方形波を含む交流信号の大きさは「実効値」で表す約束になっています。
しかしながら、交流信号として最も一般的な正弦波の計測を想定した計測器では、正弦波の平均値を検出した後にその値(平均値)を実効値に換算(π/2√2 = 1.11倍)して表示する「平均値応答・実効値指示」方式を採用しているものが多数存在します。
この平均値応答・実効値指示方式の計測器(電圧計など)に方形波を入力した場合、その指示は本来の方形波の実効値とは異なった値になります。
さらに、方形波は多くの場合直流分を含みますが、交流計測器の多くは入力がAC結合されているため、直流分を除いた値が表示されます。
直流分を含む値を求める場合は、直流分だけを取り出して別途計測し、両者の二乗の和の平方根から算出します。
以下にAC結合された方形波の実効値と平均値そして平均値応答・実効値指示方式の計測器での指示の関係をまとめてみました
平均値応答・実効値指示による誤差を解決するために、デジタルマルチメータなどでは、どのような波形でも実効値を指示する「実効値応答・実効値指示」方式を採用した機種も増えています。
このタイプの計測器は真の実効値指示(ture rms responding)などと呼ばれ、方形波でも実効値が表示されるので便利です。
ただし、計測器の周波数特性が方形波の高調波周波数まで十分に伸びていることが条件であることは言うまでもありません。
また、多くの場合、クレストファクタ(波高率)に制限があります。
クレストファクタのクレスト(crest)とは、ニワトリのとさか(鶏冠)や山の頂などを意味し、クレストファクタは、波形の「尖り具合」を表す指標として使われています。
波形の尖った信号では、実効値(計測器の指示値)が計測レンジの範囲内にあっても、ピーク値がレンジの最大値を超え飽和してしまうことがあり、大きな誤差が発生します。
クレストファクタは具体的には、信号の実効値とピーク値の比率として定義されます。
上の表と図からは、デューティ50%の方形波のクレストファクタは1になることが分かります。
さらに、デューティが30%の時のクレストファクタは約1.5に、10%では3に、2%で7になります。(AC結合)
ちなみに、正弦波のクレストファクタは1.4(=√2)、三角波では1.7(=√3)です。